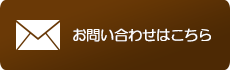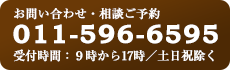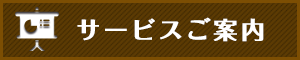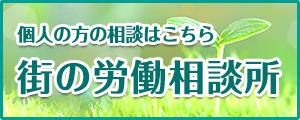今日、このようなネットニュースが出ていました
「助成金狙う悪徳社労士、コロナ禍の「雇調金バブル」で相次ぐ…3年間で64人が関与・刑事事件にも」(読売新聞オンライン)
ネットニュースで「社労士」の文字を見たのは、数ヶ月前にMrs.GREEN APPLEの元ドラマーの方が社労士になったという明るいニュース以来だったので、今度は暗いニュースで悲しいです。
記事の中で気になった箇所を2つ。
「社労士が企業側の虚偽申請を見抜けずに関与してしまったケースもある一方、積極的に企業側に働きかけるなどして不正を主導した例も目立つ。」
この記事のとおり、自ら積極的に不正をしただけでなく、程度の問題はありますが「見抜けずに関与してしまった」場合も不正とされる可能性があります。ちょうど今日社労士会から届いた会報にも、事務所の職員が虚偽に作成した賃金台帳とタイムカードを社労士が確認しなかったので懲戒処分を受けたとの記載がありました。
弊所には時々、「助成金の申請を代行してもらえませんか、何件か他の社労士さんに電話を掛けたのですが、うちは助成金をやってないと言われまして…」という電話を頂きます。
社会保険労務士法第20条では「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。」と定められているので、本来は理由なく断ってはいけないにも関わらず、助成金をやらない社労士が多いのが実情です。
何故このような定めがあるかというと、社会保険や労働保険に関する手続代行業務は「独占業務」と呼ばれ、社労士以外の者が業として行ってはいけないのです。すなわち企業が誰かに申請代行を頼みたいと思ったら、社労士にしか頼めないのです。社労士にしか頼めないのに社労士が断ってしまったら、企業は誰に頼んでいいのか困ってしまうので、だから社労士は正当な理由なく依頼を拒否してはいけないのです。
しかし実態としては助成金というだけで断る社労士がとても多い。その理由は、上記に書いたとおり、積極的に不正に関与しなくても見抜けなかっただけで懲戒を受ける怖さがあるからです。その怖さはすごく良くわかります。なので助成金を一切やらない社労士を私は責めることは出来ません。
なお弊所は、「顧問先様に限り助成金を受ける」というスタンスです。日頃から帳簿を見て、不正なことが感じられない信頼できる企業様だからお受けするというやり方にしています。これならギリ社会保険労務士法第20条違反にならず、不正関与も何とか防げるかなと考えています。上記のようなお電話を頂いたときは、そのように説明しています。
記事の中での気になった箇所もう一つ。
「全国社会保険労務士連合会は、定期的な倫理研修の受講を社労士に義務付ける。研修はオンラインでも受講可能だが受講しない社労士もおり、同連合会は「受講率が100%に達しないのは課題。引き続き社労士の品位保持に向けた取り組みを進めたい」としている。」
この記事は間違っています。「オンラインでも受講可能」でなく、「オンラインでしか受講できません」。
コロナをきっかけに全員オンラインでの受講になり、今でもそれが継続しています。
私としては実地研修に戻すべきだと考えます。オンラインだから不真面目、実地だから真面目に受けるというのも決め付け過ぎですが、どうしてもオンラインは流しているだけで受講したことになるので、実地の方がより成果は上がると思います。更に、一方通行だけでなくゼミナール方式やディベート方式も入れると、より良いと思います。
私は特定社労士(社労士の人が受験する上位資格)のグループ研修のリーダーを毎年させて頂いており、その中で倫理のディベートもあるのですが、倫理規定についてそこで初めて知ったという人が毎年います。社労士を既に持っているという人ですらそうなのですから、連合会は本気で品位保持に努めたいと考えるなら、受講率100%は勿論のこと、真剣に倫理研修の実地化と研修方式の見直しについて考えるべきだと思います。
あと倫理研修を受講しない人対策としては、受講しない場合に懲戒などのペナルティを課せば良いだけだと思います。「助成金の不正を見抜けなかった」という過失だけで懲戒にするのなら、「倫理研修を受けない」という故意に対して懲戒を課すのは全く問題ないと思いますが…。